
今回は、以前にお問い合わせがあった内容と類似しておりますが【嫌われないか不安】との観点が違うとのお声を新たにいただいたのでお伝えさせていただきます。
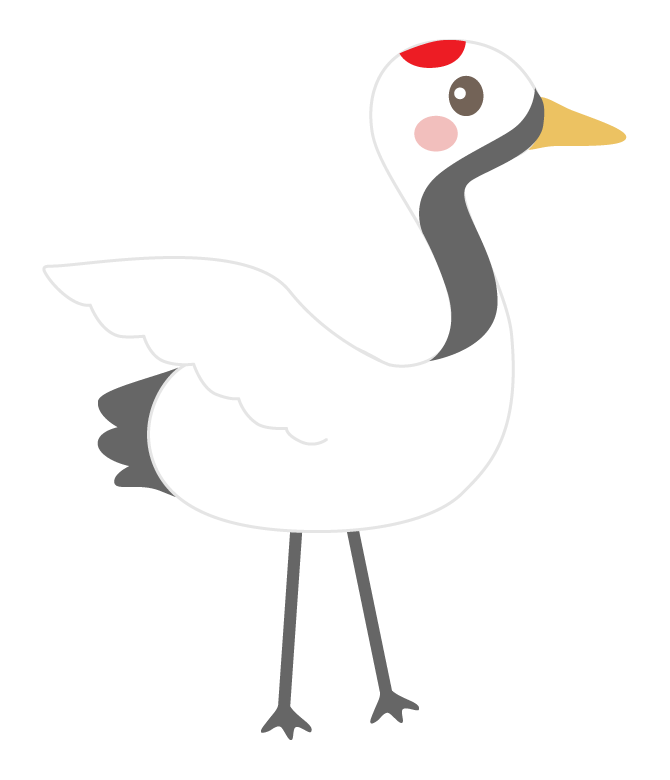
これが以前のお問い合わせだね
カウンセリングで上手く話せない!の解決法♪
まず、カウンセリングでうまく話せないと感じることは多くの人が経験することであります。
しかし、その背景にはさまざまな心理的要因が関わっており、カウンセリングで話しにくく感じる理由や、その克服方法について説明していきます。
話しにくい心理的な要因
評価不安
これは、以前にお問い合わせがあった内容と同じですね。
カウンセラーに「自分がどう思われるか」という評価不安があり、話しにくくなる要因の一つです。
「社会的自己意識」と呼ばれる心理的要因によって、人は他者からの評価や視線を強く意識し、それに対する不安を感じることがあります。
「こんなことを話したらカウンセラーに変に思われるのではないか」という懸念が、話を抑え込む原因となる場合があります。
不安感や緊張
これは、誰にでもあり得る『不安』や『緊張』ですね。
カウンセリングの場面では、自分の悩みや内面を見せることに対する不安感が生じやすいです。
特に初対面のカウンセラーに自分のプライベートな部分をさらけ出すのは、多くの人にとって大きな挑戦となります。
想像していただければ分かると思いますが、不安や緊張が高まり過ぎると心拍数が上昇し、思考の流れが停滞して話がスムーズに進まなくなります。
このため、話したいことがあっても言葉が出にくくなってしまうのです。
自己開示への抵抗感
カウンセリングは自己開示をする場となりますが、自己開示には抵抗感が伴います。
当然ですが、自己開示の程度や内容には個人差があり、自己開示に対する抵抗が強い人ほど、話がしづらくなる傾向があります。
これは、過去の経験や環境によって形成されます。
特に自己開示に慣れていない人や、他人に弱さを見せることに抵抗がある人にとっては、大きなハードルになってしまいます。
感情のコントロール
自分の悩みや感情について話すことが求められる場面では、感情を抑制しようとする傾向が強まる場合があります。
「感情をあまり表に出さないほうが・・・」「泣いたら恥ずかしい」「思い出すと気分が悪くなる」等、感情をコントロールしようとし言葉が詰まる原因になることがあります。
このような感情の抑制は、思考と感情の流れを分断させてしまい、スムーズなコミュニケーションを妨げることが知られています。
話しやすくなるためのアプローチ法
ここからは、改善方法についてご案内していきます。
リラックス法
一般的には、深呼吸やストレッチを取り入れることは、不安や緊張を軽減するのに有効とされています。
カウンセリングの前に深呼吸を行ったり、手や肩の筋肉を意識的に緩めることで、リラックスした状態を作り出せます。
他にも、前日の睡眠やアロマ等の香り、心地よい音楽もありますよね。
リラクゼーションは「自己調整力」を高める効果があり、話しやすい心理状態をサポートします。
自分にとってリラックスできる方法を見つけるのも良いです。
メモを活用する
これは、実際に活用していただいている方は多いです。
事前に話したい内容をメモにまとめ「どのような悩みについて話すのか」「その悩みに対してどんな感情があるのか」を簡単に箇条書きにしておきます。
また、カウンセリング中に話が詰まった時にもメモを見返すことで、気持ちを落ち着けたり話の流れを思い出したりするのにも役立ちます。
「話せない自分」を受け入れる
森田療法と言われる療法のひとつです。
「話せないこと」自体もカウンセリングで扱うべきテーマと捉えるます。
話しにくさを感じる背景には、過去の経験や環境、受け取り方が影響していることがあり、そのような「話せない自分」を受け入れることもカウンセリングの進展に繋がります。
心理学の「セルフ・アクセプタンス(自己受容)」を行い、話せない自分も自分の一部として受け入れると、不安や抵抗感が和らぐことがあります。
小さなことから話す
重要なのは、カウンセリングでは、完璧に自分の悩みを伝える必要はありません。
ご自身の感情として「もどかしい」「悲しい」「イライラする」等の感情が芽生えるかもしれませんが、まずは【話す内容や言葉の選び方にこだわりすぎず、まずは感じたことや印象に残っている出来事】等から話し始めましょう。
心理学的にも「徐々に自己開示を進める」ことが効果的だとされています。
少しずつ話をすることで、自己開示に対する抵抗が減り、話しやすい雰囲気が生まれてきます。
カウンセラーとの信頼関係を築く
信頼関係の構築は、話しやすい環境を作るために重要です。
前述の【小さなことから話す】にも関わってくることですが、そこから信頼関係を築くこともできます。
心理学では「ラポール形成」という概念があり、これはお互いの信頼と共感が生まれる状態を指します。
信頼関係が深まると、安心して自己開示できるようになるため、話しやすさが増します。
信頼関係を築くには、カウンセラーが話すことにしっかり耳を傾けているかどうか、また自身がそのカウンセラーと相性が良いかどうかも大切な要素となります。
実際の練習方法と心得
実際に話しやすさを高めるためには、「話す練習」を重ねることも重要です。
先程の【メモを活用する】もその1つですが、それ以外も簡単ながら案内していきます。
ご参考にしていただければ幸いです。
鏡を見て話す
鏡に向かって話をすることで、自己開示の練習になります。
これにより、自分の感情表現や言葉の使い方に慣れ、自己受容を高めることができます。
日記をつける
ここでの日記は一日の出来事を記録するのではなく、日々の感情と一緒に出来事を記録することで、感情の整理が進みます。
『出来事があった時に自分はどんな感情になったのか!』
を記録します。
この感情日記は、自分の気持ちを言葉にする力を養うのに役立ち、カウンセリングでの話しやすさに繋がります。
自分対する肯定的なイメージ
自分自身を受け入れる言葉や、自分に対する肯定的なメッセージイメージします。
このイメージを心に刻むと、不安感や緊張が軽減されやすくなります。
これは、話しにくさを和らげる効果があります。
カウンセラーとの協調
カウンセリングは、クライエント(相談者)だけで解決していく訳ではございません。
カウンセラーの役割は、話しやすい環境を提供することも必要です。
そのため、カウンセラーはクライエントの話しにくさに気づき、適切なサポートを提供してくれます。またはしなければいけますん。
たとえば、話しにくいと感じている場合には「話したくない時は無理に話さなくてもいい」という安心感を与えたり、「どんな些細なことでも聞きます」といったサポート的な言葉を使ったりすることが効果的です。また、カウンセラーが積極的に質問することも、話を引き出しやすくするための一つの方法です。
前述でもありましたが、カウンセラーとのコミュニケーションが良好であるほど、話しやすいと感じられるようになります。
そのため、カウンセリングの中で「話しにくい」と感じる時は、正直にその気持ちを伝えることも大切です。
カウンセラーはそのフィードバックを受け取り、クライエントに合った進め方を提案してくれるでしょう。
まとめ

今回は、クライエントが準備できることを多くお伝えできればと思い、
書いています。
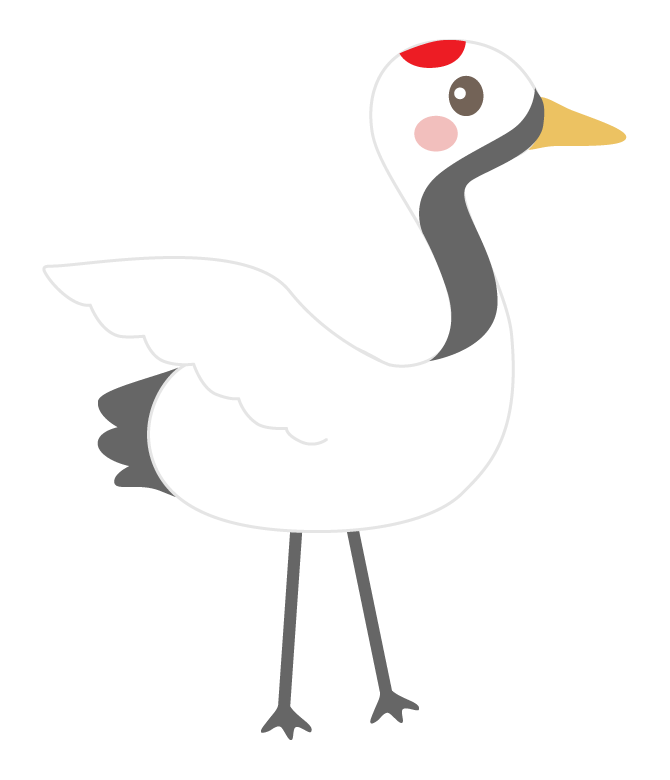
少しでも、参考にして貰えると嬉しいね

そうだね。
カウンセラーとの相性もあるし、相談する側の不安が大きくならないようにしなきゃですね。
先程もありましたが、カウンセリングはカウンセラーと一緒に行うものです。
上手く話しをする必要はないですが、感情や気持ちを素直に表現できることは大切ですね。
勿論、カウンセラー側が気持ちを察してくれたり、気持ちを汲んでくれたりしてくだされば良いですが、それが出来るのは相性の影響もあるかと思います。
皆様にとって少しでもご参考になれば幸いです。




コメント